美術やArtは、時に言葉以上に物事や心情を雄弁に語ることもある。
でも、だからと言って人間が言葉を持たずArtが言葉の代わりになるとは思えないし、日々、美術やArtのことについて、この世の全体と関係付けながら考えているにしても、そうした思考はすべて言葉によって支えられている。
Art・美術に限らず、物事を論理的に思考したり自らの心象を咀嚼したりする時、そこに言葉がなかったらどうなるのだろうか。
もしも言葉が無かったら、物事・事象への詳細な意味づけが困難となって、他者へ伝えるすべもない…ということになるのだろうか。
ある研究で、言葉を持たない動物や赤ちゃんの脳の動きを観察すると、どちらも共に「考えている」と推測できる動きがあるそうだが、生まれて直ぐは動物と人間に大きな違いはないのだそうだ。しかしやがて人間の赤ちゃんが人間の言葉に触れ、自ら言葉を使い始めるようになると、人間と動物の違いが明確になり始める…。
それは当然と言えば、当然のことのような気がしてしまうけれど、でも、ありとあらゆる様々な音が溢れている状況の中から、ある特定の音だけを言葉として認識し、そしてその言葉を自らが使い始めるということは、様々な音の中からある規則を満たすものだけを言語として選別出来る力が人間の遺伝子の中に備わっているということでもあって、それこそが人間と人間以外の動物との最も大きな違いであるのだと思う。
…。
だからと言って、他の動物よりも人間が優れているということではなくて、あくまでも生命に備わった違いでしかない。
人間はこの違いによって言葉を使って思考することが出来る…というか、言葉に人間の命は支えられているということでもあって、それと言うのは逆に、言葉を待たずに生きる他の動物が持つ力を人間は持っていないということではあるものの、社会の現況(多くの野生動物や植物が絶滅の危機に瀕している状況や自然に対する人間の都合優先の開発行為)からすれば、人間はこの世のすべての生命の頂点に君臨していると思い込んでしまっていると思わざるを得ない。
言い換えればそれは、この世の生命全体に対する独裁体制 (権威主義体制)が敷かれているということであり、そうした体制下で人間は言葉による暴力的支配を実行していると同じだ。
Artという概念が西洋社会に誕生したのはたかだか200年ちょっと前のこと。
その概念が日本に伝わり、そこに芸術と美術という言葉が訳語としてあてがわれたことで、日本人はArtと美を同義、あるいは、美と関係付けて理解しているけれど、元々のArtという概念は日本人の理解とは異なるものだ…。
言葉は時代と共に変化する、地域性を兼ね備える性質があるので、西洋概念であったArtという概念が日本に伝わり、そこで日本に即した概念と融合し、元々の概念とは異なる言葉の意味を備えたからといってそれを間違いとは言えない。
かつて明治時代、日本に大量に流入した西洋概念は勿論Artに限らないけれど、そうした概念に対して日本人としての概念に即した言葉(訳語)をつくり出した人々の苦労は相当のものであったと思う。
言葉とは何か?ということを考えれば、それまでの日本語の中に無い概念とは、それまで日本人はそういった考え方をしたことが無かったということであって、それと言うのはようするに、“それまでの日本には必要が無かった“ということ。
必要の無かった概念に対して言葉をあてがうというのは、新しい考え方をつくる ということでもあって、その考え方=言葉がその後の日本をつくるということであったはずだ。
欧米列強が植民地支配力を拡大し、東アジアにその勢力圏を広げようとしてきていた時代。
当時の日本が富国強兵を掲げ、欧米列強に劣らない国へと舵を切る最中、西洋概念に対して日本語としての概念、新しい日本語をあてがうことは、正に国策としての最重要な必要性であったのだと思う。
いま現在を生きる私たちが、その時代につくられた言葉をあたりまえの言葉として使っているだけでは、かつてそれに携った人々の苦労や、そこに秘められた想いを知る由もないけれど、そうした言葉を使うことによって実はそうした言葉に託されたであろう想いを日本語として取り入れ、そして思考しているとも言える。
そういったことについて考えてしまうと、Artという英語は日本語で美術・芸術だと単純に訳す気にはなれないし、職業は?と聞かれて「Artistです」とは素直に答えたくない自分がある。
Artに対してなぜ芸術という言葉があてがわれたのか?その後、なぜ美術という言葉がつくられたのか?
Wikipediaで調べる程度ではそうした背景には辿り付けないけれど、かつて紙幣の顔にまでなった夏目漱石でさえ、当時の日本の急激な変化について、小説をとおして憂いている…。それはきっと、言葉とは何か?ということについて考え抜いたからこその想いであったのであろうし、小説家だけでなく、当時の多くの表現者達は皆、言葉を極めて大切に扱っている…。
Artが芸術であり美術であると翻訳されることは否定しないけれど、Artと出会い、美術家を名のる自分としては、少なくともArtistではなく美術家でありたいと思っているし、…であるとするならば、美という言葉が持つ意味がこの世から失なわれないために、いま自分が何をすべきなのかについて考え続けたいと思う。


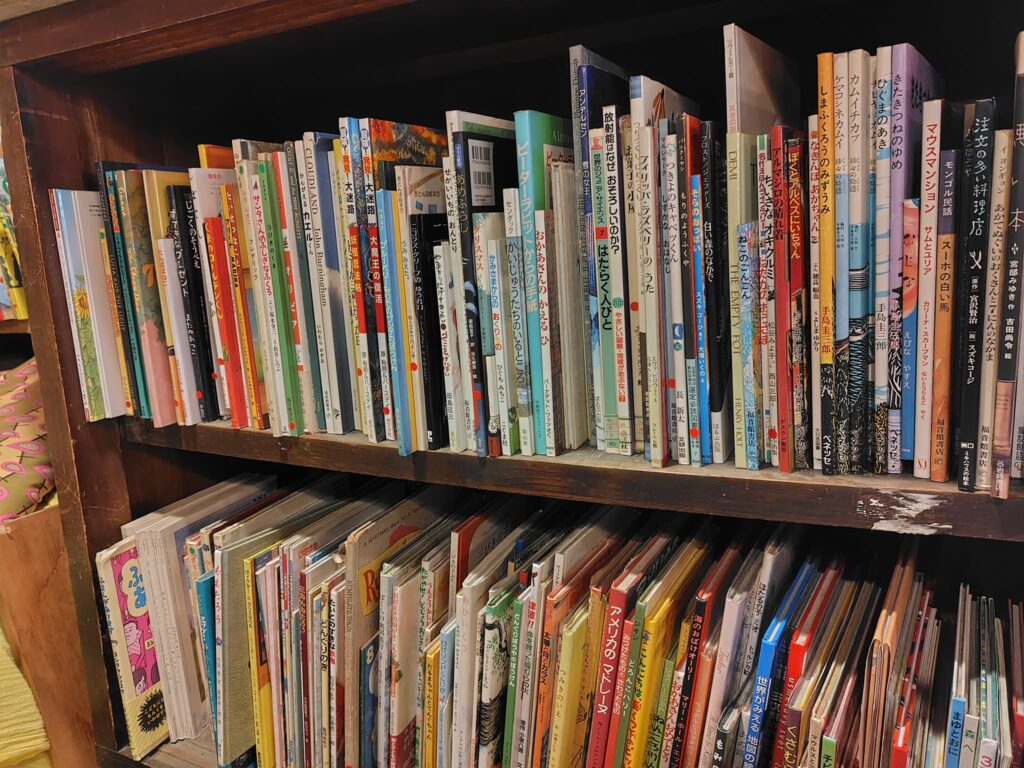

コメントを残す